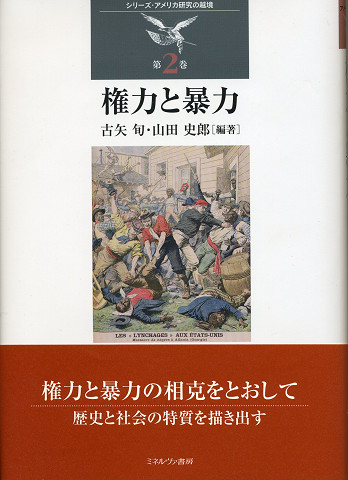
- 『権力と暴力 シリーズアメリカ研究の越境 第2巻』 古矢旬・山田史郎編著
2007年6月30日刊 ミネルヴァ書房 定価3500円 -
★ 本書は、2006年に創立40周年を迎えた「アメリカ学会」の記念事業の一環として企画されたアメリカ学会員計70名の執筆者が参加した「シリーズアメリカ研究の越境 全6巻」の第2巻です。はっきり言いまして、同シリーズの既刊のものと比較しまして、この巻は面白いです。読んでいても退屈しません。ほんとです。もちろん、本書は研究書であって、アメリカ学会の会員が、丹念に資料にあたって整理して紹介した論文を集めたものです。「言論」ではありません。「だから、何だよ?それで?」と、つっこむほうが、おかしいです。悪しからず。
★ 拙論(以下に冒頭部分が紹介されています)は、去年の夏に書いたものです。私にとって初めて書いて活字になった「文学研究系ではない論文」です。アイン・ランドに出会ってから、政治思想や法学のことなど自分なりに勉強してきまして、そろそろ分野のトラヴァーユをしてもいいよな・・・と勝手に思って試みました。ただし、自分で、自分の書いたものの水準がわかりません。ですから、今回は、どなたにも献本しておりません。お読みになりたい方はご連絡ください。贈呈させていただきます。誰もいないよな・・・
★ 2006年9月の始めに予定していた天津・北京旅行を出発当日にキャンセルするはめになったのは、この論文が未完成だったからでした。たとえ5流どころの研究者でも、論文書き上げるほうが、海外旅行よりも、はるかに喜びが深くて大きい・・・白内障になったのも、この論文用の資料読みのせいだ・・・
第III部 グローバル化社会と暴力
第十章 自由の帝国に「女」は住めない
----武装権から考える「アメリカのフェミニズム」---
藤森かよこ第一節 「アメリカのフェミニズム」なるものの暴力志向
(1) なぜ、「アメリカのフェミニズム」は批判されるのか本論の目的は、アメリカ合衆国憲法修正二条が規定する武装権(the right of the people to keep and bear Arms)の観点から、「アメリカのフェミニズム」を擁護することにある。「アメリカのフェミニズム」の可能性を指摘することにある。言い換えれば、「アメリカのフェミニズム」が潜在的に持つ要素の今日的意義、グローバル化が進行する世界における、その意義を提示することにある。
「アメリカのフェミニズム」に対する批判は少なくない。エリザベット・バダンテールは、アンドレア・ドウォーキンやキャサリン・マッキノンに代表されるアメリカのラディカル・フェミニストは、フランス人女性相手には売り物にならない、極端すぎて笑われるのがおちだと語る(バダンテール、二〇〇六、一六九頁)。男による女への暴力に対処するアメリカのラディカル・フェミニストは、性犯罪者や変質者だけを訴えるのではなく、人類の半分にあたる男全体をまるで悪の権化そのものであるかのように糾弾していると批判する(バダンテール、二〇〇六、二五頁)。
エマニュエル・トッドは、「アメリカのフェミニズムは年を経るにつれて、ますますドグマ的かつ攻撃的になっており、世界の実際上の多様性に対するアメリカの寛容は、絶えず低下し続けている」(トッド、二〇〇三、一九一頁)のであり、「ヨーロッパ人とアメリカ人の文化的差異はほとんど無限に枚挙できるが、人類学者としては、去勢コンプレックスを植え付ける恐ろしいアメリカ女性の地位は、ヨーロッパの男たちにとっては、アラブの男の全能の権力がヨーロッパ人女性にとって不安なものであると同様に、不安を感じさせるものであることを指摘しておかねばならない」(トッド、二〇〇三、二四五頁)と書く。
フェミニズムの歴史と運動を総括して未来への展望を示しているエステル・フリードマンは「有色の女性にとって、フェミニズムは、ときに人種の正義の運動と競争するものであるように思えた。かつて植民地であった国や発展途上国では、フェミニズムへの恐怖ではないにしても疑念が、西洋のコロニアリズムとフェミニズムを結びつけることになったかもしれない」(フリードマン、二〇〇五、四一頁)と指摘して、「アメリカのフェミニズム」とは、非西洋圏フェミニストにとっては、「現代西洋のもっとも悪い特徴と結びついた凶暴な個人主義の一形態」(フリードマン、二〇〇五、四一頁)と推測している。
言うまでもなく、フェミニズムは一枚岩ではない。移民国家であるアメリカならば、女と階級に人種や民族の偏差が加わるのであるから、アメリカのフェミニズムの多様性の度合いは他国とは比較にならない。だから、「アメリカのフェミニズム」と呼ぶような、明確に限定された実態などはない。しかし、前述の批判者の発言から判断する限り、「アメリカのフェミニズム」とは、雑駁に言えば、「リベラル・フェミニズム」であり「ラディカル・フェミニズム」を示すようだ。
これらのフェミニズムが、「アメリカのフェミニズム」として批判される理由は、その暴力も辞さない闘争的姿勢である。たとえば、「全米女性機構」(NOW)に代表されるリベラルフェミニストの多くは、女性兵士を肯定している。一般的には、ナオミ・ウルフの『火には火で(眼には眼を)』(Wolf,1993)のように、女が自分の持っている力(まさに物理的、肉体的力)に目覚め、暴力男には反撃せよと女たちに訴えるストリートスマート・フェミニズム系の本は多くの読者を獲得している。マーサ・マッコーヒィーの『リアル・ノックアウト――女性の自己防衛のフィジカル・フェミニズム』(McCaughey,1997)のように、肉体を鍛錬し訓練することによって、自らの力を認識することを説く本も、多く出版されている。
(2)なぜ、「アメリカのフェミニズム」は暴力を辞さないのか?上野千鶴子は、「市民権とジェンダー」という論文において、フランス革命までさかのぼり、人権概念のジェンダー性と階級性と排他性を指摘し、人権概念から派生した初期のフェミニズム(リベラル・フェミニズム)が、女性の市民化=女性解放と考え、「男なみになりたい&ならなければならない」志向を持たざるをえなかったことを指摘した。国民国家における市民の義務のうち重要な二つが、納税と兵役ならば、上野が指摘するように、国民国家のナショナリズムと、「(男なみ)リベラルフェミニズム」が結びつくとき、期待される「女性兵士」が誕生する。女性兵士が反国家に転じれば、「革命の女戦士」もしくは「女テロリスト」になる(上野、二〇〇六、三〜三四頁)。
このような「(男なみ)リベラル・フェミニズム」の運命(論理的帰結)以外に、「アメリカのフェミニズム」を「アメリカのフェミニズム」ならしめているアメリカ的要素のひとつが、憲法修正二条が規定する武装権である。兵士でもなく、警官でもなく、テロリストでもないのに、アメリカには武器を所持する女たちが多くいるのは、この法が市民の銃所持を基本的人権のひとつとして保障しているからである。より正確にいえば、次節で言及するように、保障していると解釈されているからである。
(本書pp.229-233より勝手に転載)★ご注文は以下のサイトで
amazon.co.jp